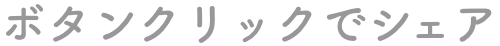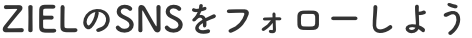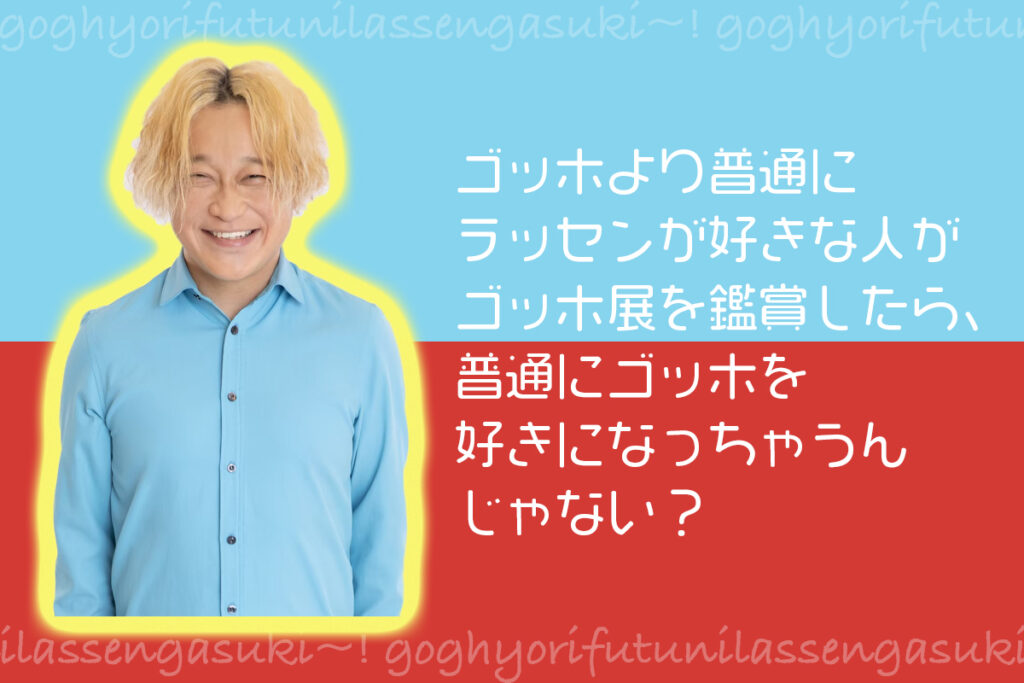大切な人との別れ――その瞬間を納得できるのか
いつ訪れるかわからない「死」の受け入れ方
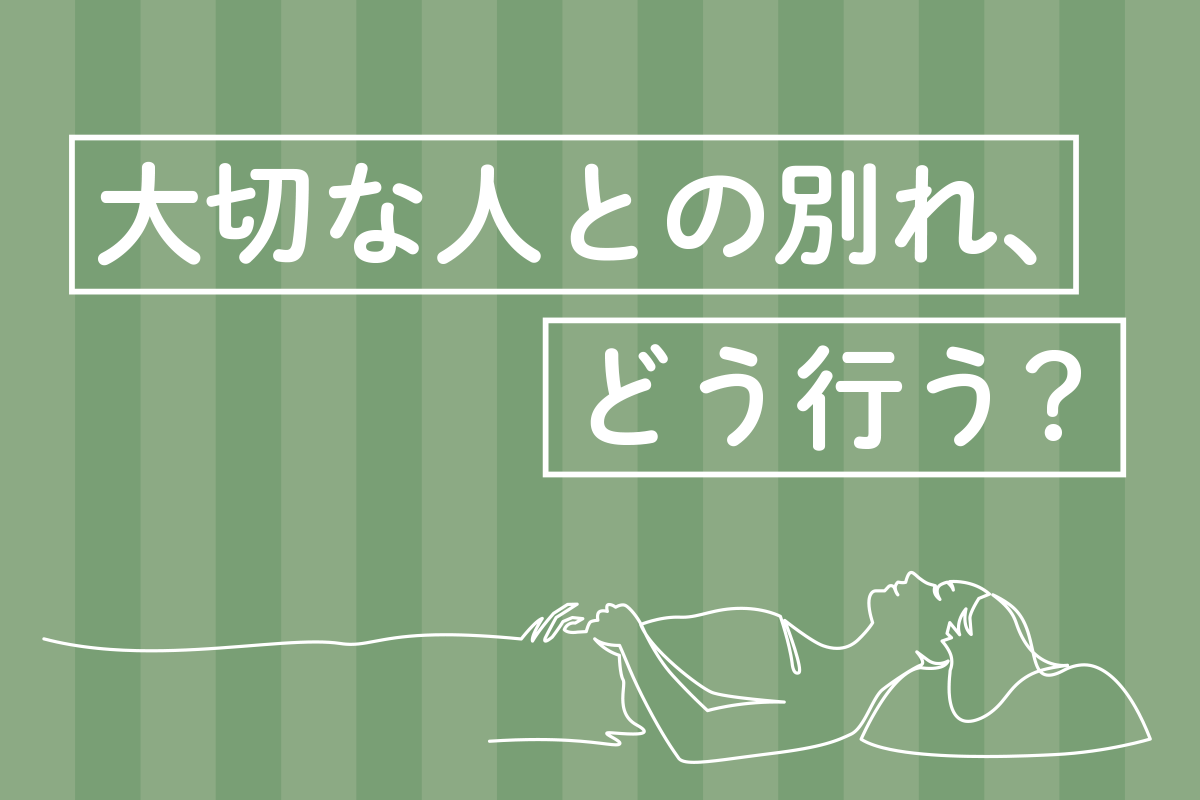
取材・文:出口夢々
いつ訪れるかわからない人の「死」。大切な人との最期の別れはどのように行えるのか、また遺された人の気持ちを救えるような別れ方とはどのようなものなのしょうか。
そこで、ある日突然夫を亡くした経験のある死生学研究者の小谷みどりさんに、その経験を経て思ったこと、考えたことや、いつ訪れるかわからない自分の死をどのように考えているか、伺いました。
納得のできる死などない
――小谷さんはご主人をある朝突然亡くされましたが、その死を納得することはできたのでしょうか?
死には、「さようなら」を言って亡くなることのできる死と、強制終了の死がありますよね。どちらにしても、納得して見送れることなどないと思います。
私はある日突然夫を亡くしました。目が覚めたら夫が亡くなっていたんです。朝、別の部屋で寝ていた夫を起こしに行ったら息がなくて。だらりとベッドからぶら下がった腕に死斑が出ていたので「死んでいる」とすぐにわかったのですが、なかなか理解が追いつかなかったんですよね。なんで死んでいるのかわからないから、「おかしいな、昨日の晩は話をしたはずなのに」「もしかして、私が殺した?」「ありえない、私が先に寝たんだから」と、とにかく混乱しました。
とりあえず救急車を呼んだのですが、すでに息を引き取っていたので救急隊員の方が警察に連絡をして、家に刑事さんが来ました。そして検視をすることになり、葬儀社に連絡をして……あれよあれよという間に夫は遺骨になったんです。
こんなに急に夫を亡くして、納得するも何もないですよね。突然いなくなってしまったので、「なんで死んでしまったのだろう」という疑問が頭にまとわりついて離れませんでした。数年に一度しか風邪を引かなかった人でしたし、亡くなる数週間前に行われた健康診断でも異常はなかったんです。
ですが、亡くなる1週間前に「忙しくて死にそう」と夫が言っていたのを思い出して。そこから「なんで死んだのか」をはっきりさせるために、弁護士に依頼をして過労死申請をしました。申請から約1年後には労災認定を受けましたが、今でも夫は死んだのではなく、ジンバブエに出張に行っている感覚です。もともと出張の多い人だったので、一時的に私の近くにいないだけのような気がするんですよ。
私は夫を突然失ったわけですけど、闘病の末、大切な人を失われる方もいますよね。病気が発覚したときには「こんなにがんが進行していたのに、なんで気づいてあげられなかったんだろう」とか「体調が悪そうなのはわかっていたのに、どうして早く病院に行けって言わなかったんだろう」と後悔される方も多いと思います。
私の知り合いに、1カ月前に奥さんを亡くした方がいるんですけど、その奥さんは末期がんと診断されてから3年ほど生きられたんです。なので、奥さんが余命宣告を受けてからは、みそ汁のつくり方を教わったり、いろいろなところに旅行したりと、たくさんの時間を一緒に過ごしたそうです。ですので、奥さんを失ったことで落ち込んではいますけど、納得いく別れをしたとは言っています。
ですが、納得していることと悲しいと思うことは、別ものなんです。大切な人を亡くしたときにはそれを理解するしかありませんが、理解できたからと言って悲しみを覚えないわけではありませんよね。だからこそ、元気なうちに家族への感謝の気持ちや伝えたいことを書き残しておいたり、直接伝えておくことが大事だと思います。
――病気になった後ではなく、元気なうちに行動しておくのですね。
死に方は選べませんし、強制終了の死の場合には、死に向かっていく時間を大切な人と共有する時間がありませんからね。
また、病気になって余命宣告をされた場合でも、大切なことは伝えにくいと思います。本人は言いたくても、遺される家族は「そんなこと言わないでよ」「また今度聞くから」とはぐらかしたくなりますよね。それに、遺される人もそのような状況で、「何か言い残したことはないか」とか「お母さんの得意料理のレシピ教えて」とは言えないですよね。元気だったときなら聞きやすいことも、相手に死が迫っているとわかった状態では聞けないんですよ。だから元気なうちに行動するんです。
死を受け入れる必要はない
――先ほど「夫は亡くなったのではなく、ジンバブエに出張している感覚」とおっしゃっていたのが印象的でした。
もちろん、夫が死んでいることはわかっているんですけど、感覚としてはどこかへ出張に行っているような気がしてならないんですよね。ある日突然、夫が家出をしたようなイメージです。死体は見ていますけど、なんで突然死んだのかがわからないから、どこかで生きているように思ってしまう。
でも、それでいいと思っているんです。よく「小谷さんは死を受け入れていないんですね」と言われるんですけど、天国に行ったと思っていれば「死を受け入れている」と思われて、ジンバブエに行ったと思っていれば「死を受け入れていない」と思われることに疑問を感じています。
そもそも、「死を受け入れる」という考え方はアメリカから輸入したものなんです。キリスト教圏であるアメリカでは、死者は神の国へ行ったとみなされるので、家に仏壇も置いていないしお墓参りもしないんですよね。だから、「もう二度と会えない」という事実を受容しなければならないという文化があるんです。
ですが、日本の場合はそうではないですよね。家には仏壇があって、ご先祖さまの写真が壁のうえに並べてあって、死者が戻ってくるために迎え火をする文化があって……。また、「亡くなった人が見守っていてくれている気がする」とか「心のなかにいる」とか言う人も多いですよね。ですので、亡くなった人と生きている人がある意味では共存し続けているんですよ。
大切な人の死に囚われすぎてしまって自分の人生が前に進まないのであれば問題はあるかもしれませんが、そうでなければ「死を受け入れる」ということに固執する必要はないと思います。
――ご主人を突然亡くされて、小谷さんの人生はどのように変わりましたか?
何が原因で死ぬか、何が起こって死ぬかわからないからこそ、「いつか」とか「そのうち」という言葉を使わないと決めました。いつ死ぬかわからないからこそ、自分のやりたいことや夢を先延ばしにしないと決めたんです。
私は去年会社を辞めたんです。今はカンボジアで暮らす貧しくて学校に通えない若者たちに、パンづくりを教えています。昔から「アジアの貧しい若者のために、何かをしたい」という思いがあったんです。具体的な「何か」は考えていなかったんですけど、やりたいからやろうと思って。
死後のことや家の生前整理も大事かもしれませんが、私にとっては生きているからこそできることのほうが大切です。そこにフォーカスを当てているので、いつ死がくるかわからないからこそ、やりたいことは先延ばしにしない、そう決めました。
記事の感想をコメント欄で教えてください!
この記事に協力してくれた人special thanks
-
小谷みどり
シニア生活文化研究所所長。 大阪府出身。博士(人間科学)。専門は生活設計論、死生学、葬送問題。奈良女子大学、立教セカンドステージ大学で講師をするほか、身延山大学、武蔵野大学の客員教授も務める。最近の著書に、『〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓」(岩波新書、2017年)、『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』(新潮社、2018年)など。 
まだデータがありません。