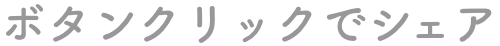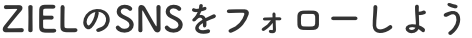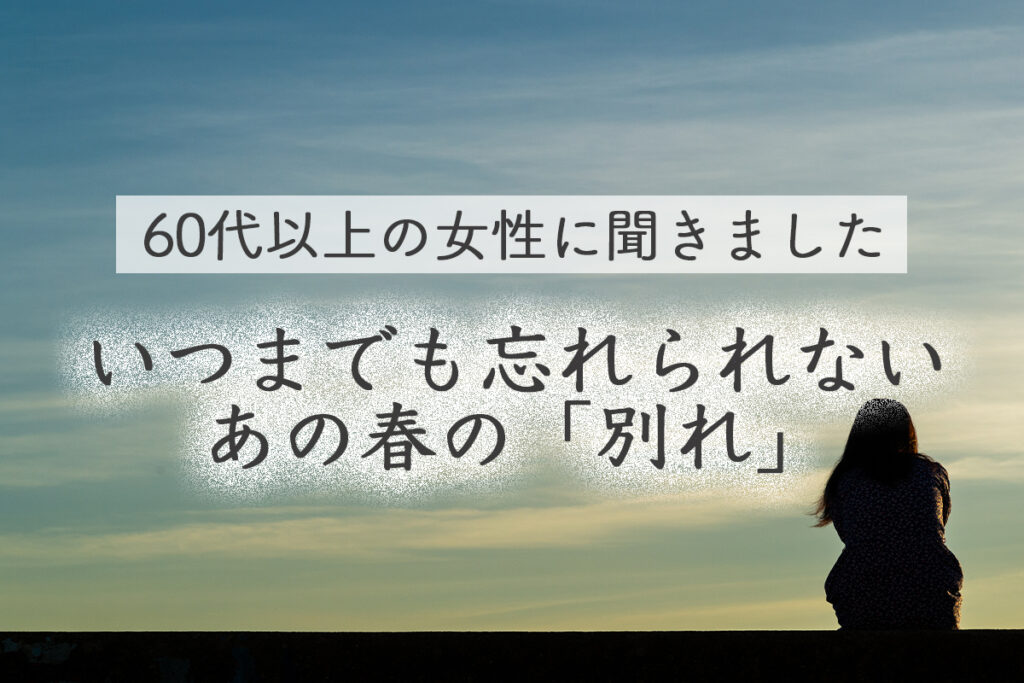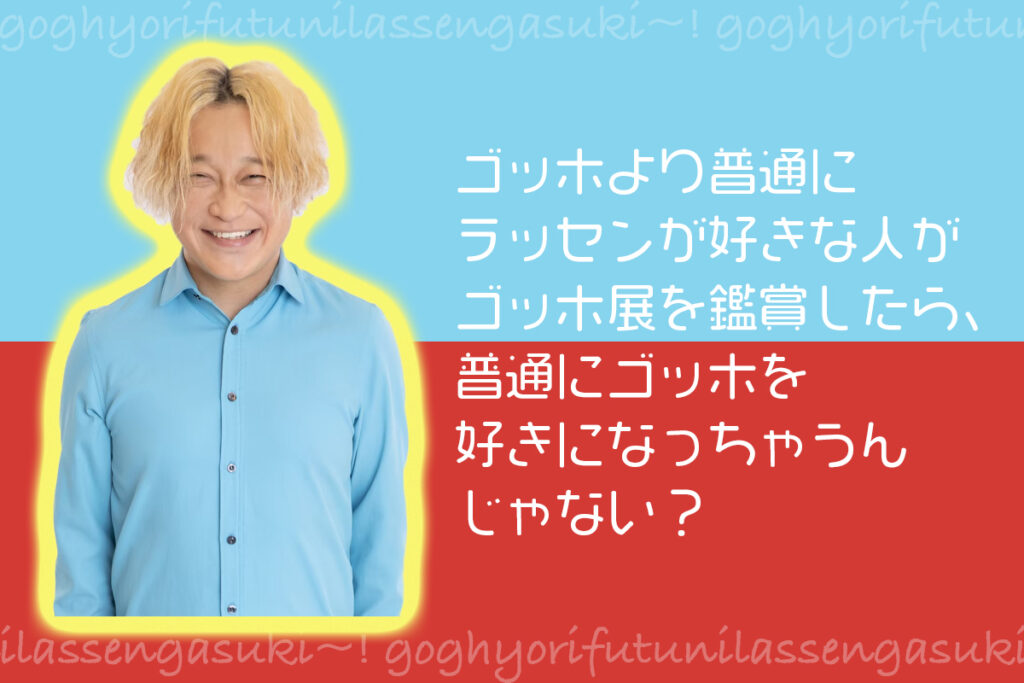小説家・白石一文さん「魂は存在する。問題は、その魂は死後にどこへ行くのか、だ」(後編)
直木賞作家が語る「自分をあたらしくする」ことと「死」の関係性

取材・文:出口夢々
写真:浅野 剛
中編で、死を「目的化」し、人生のゴールとして死を設定すれば、将来絶対に訪れる死への恐怖心を薄くできるのではないかと語った小説家・白石一文さん。後編では、私たちは死んだらどうなってしまうのか、神は存在するのかなど、「未知の世界」についてお話を伺いました。
私たちは身体という名の車を運転している
白石:『プラスチックの祈り』(朝日新聞出版)のなかで、小説家・大河内の火葬中に、彼の携帯電話から大河内夫人の携帯電話に着信が入るシーンがあります。あれは、僕が現実に体験したことをそのまま書いているんですよ。
出口:えっ。小説では宗教団体が仕組んだ出来事でしたよね?
白石:そう。でも、あれ、本当にあったことなんです。
作品に書いてあるとおりで、亡くなった親友が奥さんに電話してきました。親友の棺が火葬炉に入った直後、「ちょっと白石さん」と奥さんから呼ばれて。渡された携帯電話を見てみると、彼から着信が入っていたんです。発信元となった彼の携帯電話はどこにあるのか聞くと、奥さんのカバンのなかでした。しかも電源は入っていなかった。慌てて電源を入れるとちゃんと発信履歴が残っていて、発信時刻は棺が炉に入る直前。奥さんがカバンに手を突っ込んで何か細工をするのは到底不可能な時間帯だったんです。これにはさすがに驚きました。

白石:作中の大河内夫妻は「どちらかが先に死んで、万が一にも死後の世界というものがあったとしたら、そのときは必ず生き残ったほうに何かサインを送ろう」と生前に約束していたわけですが、この親友夫婦も実は似たような約束をしていたんです。親友はその約束をちゃんと守ったというわけです。
出口:そんなふうに死後の世界が存在するのであれば、身体が破滅した後も魂は生き続けるのでしょうか?
白石:そういう場合もあるでしょうね。ほかにもいくつか似たような体験をしているので、僕自身は魂の存在を疑ってはいないんです。
要するに我々は、肉体という名の車の「運転手」なんですよ。どこかの車庫でレンタルしてきた車に私が乗ってドライブしているのが、今の状態なわけです。身体は預かりものなので大切に扱わなくてはいけないし、それでも長く乗っていると、車と同じように古くなるし、古くなればなるほどメンテナンスをしないとうまく走れなくなる。そして、肉体という車はどんなに大事に乗っても、やはり物質でできていますから最後には壊れてしまう――つまり死ぬわけです。ですが、それに乗っていた運転手(=魂)は一緒に死ぬわけではなく、大半の人は動かなくなってしまった車を降りるだけなのだと思います。
出口:たしかに、病気により身体の一部を切り落とさなければならない、というような状況になって、たとえば右足の膝下部分を切断したとしても、自分という存在は残ります。身体は魂の容器のようなものなのかもしれませんね。
白石:ええ。これまでいろんな書物を読んできて、魂が存在することはほとんどの人が認めているな、と思うんです。死んだら肉体とともに魂もシャットダウンして何も残らないと考えている人は、サイエンティストを含め、まともに物事を考えている人のなかにはほとんど1人もいないのではないでしょうか。
では、残った魂はどこへ行くのか――。これに関してはものすごい数の議論がなされています。たとえば、10のマイナス27乗分の1秒後に消滅するかもしれないし、四十九日を過ぎた後に消滅するのかもしれない。はたまた、天国というものが存在して、魂は生前の記憶をもったままそこに引っ越すのかもしれない。
多くの人は「死んでみたら、一体どうなるかわかるはずだ」と予想をつけているんですが、こんなふうに“いろんな魂の可能性”がありますから、実際のところ、死んでもわからない部分がいっぱいあるんだろうと思います。つまり一瞬でなくなる魂もあれば、天国に行く魂もある。言葉や数式に表せるものではないので、人間は魂についてよく理解できないまま生きるしかないのでしょうね。それが人間の宿命なのです。実際、死後の魂がどうなるかについてはこれという答えは存在せず、魂にはさまざまな“その後”があるのだろうと思います。
ただ、その一方で、魂とは何か、死んだら魂はどこへ行くのかという問いにしっかりした答えを見い出した人もこの世界にはいるんだろうと考えています。そういう人たちは魂の行き先を知っているというよりも、恐らくその行き先をつくり出す、ないしはそこへ導くことができる人たちなのでしょうね。
そして、これは能力の問題で、字を読む能力がある人、ない人がいるように、魂を読む能力がある人、ない人がいるのではないかと。僕自身、この問いに関してもう何十年も一生懸命に考えていて、その経過報告を小説のなかでしています。だから、自分がまったく信じていないことは小説には書いていないんですよ。
自らアクションを起こせば人生に運命を見出せる
出口:では、『砂の上のあなた』(新潮社)や『私という運命について』(角川書店)では、「運命」を「逃れられないもの」として描いていますが、そのように感じられているのでしょうか?
白石:自分の人生というのは、いろんな意味であらかじめ「予定されていること」がたくさんあるのだろうと思いますね。
生きていると、いろんなことが起こりますよね。でも、その時点でその出来事がどんな意味をもつかはまったくわからなくて、10年後、20年後にようやく自分がかつてしでかした行為や受けてしまった行為の意味を理解し、そこに「運命」を見出すことが往々にしてあると思うんです。

白石:ですが、運命というボールを見つけ、しっかりキャッチするには、それ相応のキャッチャーミットを用意しておく必要があると思っています。たとえば、とても印象的な出来事が起こったときに「なんで自分はこんなことをした(された)んだろう」「なぜこんなことが起こったのだろう」としっかり考えておくんです。そうすると、10年後、20年後にそれに呼応する出来事が起こったときに、昔と現在とをつなげて、我が身に振りかかった一連の出来事の一貫性や意味を発見することが可能になります。
物事には必ず原因があって、結果がある。ただ、世の中の出来事はランダムに発生するので、「原因」があって「結果」がある、というようなわかりやすい構造にはなっていない。だから、原因となる出来事が起きた際にその意味をしっかり考えて、記憶にブックマークをつけておく。すると、突如どこかからボールが飛んでくるようにして何十年後かに結果(または原因)となる出来事が起こったときに、記憶がミットとなり、それをしっかりキャッチできる。
不思議なことに、人間は自分の身に降りかかってきた奇妙な出来事はすぐに忘れてしまうんですよ。でも、そういう出来事に限って重要な意味をもっていたりするので、日記に書いておいたり、スマホのメモに残しておいたほうが賢明ですね。
出口:それは出来事の詳細だけでなく、そのとき考えたことも一緒に残したほうがいいのでしょうか?
白石:そうですね。物事を誤って記憶するのを防ぐために、考えたことやそのときの感情なども記しておくのは有効だと思います。みんな、奇妙な出来事に限って忘れてしまうものですからね。
出口:ところで、白石さんの考える「運命」とは、神の存在を前提としたものなのでしょうか?
白石:神が存在するか否かはわかりませんが、何らかの意思にもとづいてこの世界が構成されているとは考えています。
今、マルチバースの考え方が流行っています。宇宙というのは単一の宇宙(ユニバース)ではなく、多数の宇宙が存在するという考え方です。この考え方に乗っかってみると、我々は何らかの統一性や規則性をもつ精密なルールに支配された非常に稀有な宇宙にいるのでしょう。それ自体はたとえ偶然であったとしても、とても整合性のとれた論理構造のなかで生きているので、それを操っている存在がいるとしか思えないんですよね。だから、宇宙を秩序立てて構成し続ける能力というものを「神」と呼ぶのであれば、神はたしかに存在するのかもしれません。
出口:では、運命も神によって決められた道筋のようなものなのでしょうか?
白石:いや、運命に関しては、神から人類一人ひとりに対して何らかの道筋が与えられているのではなく、しかし、だからといってまったく我々は“神に見放されている者”でもないのだろうと思います。運命という“際立った人生体験”は、おそらく「神」と人間との双方向のエネルギー交換によって生じているのでしょう。
生活保護を受けるときって、役所の窓口に行って申請して、国が定めた条件に合っていれば生活保護が適用されますよね? それと同じように、自分のほうから何らかのアクションを起こさないと運命というのは手に入らないと思うんですよ。つまり、規則があるからといって問答無用で全人類に適用されるのではなく、自分から行動しなければ規則は適用されない。
マザー・テレサは数多くの奇跡を起こした偉大な人物ですが、彼女もそういった規則(法則)を活用していたと思うんです。いろんな感染症の巣と化したカルカッタの路上に出て、路上に倒れた人たちに口移しで水を飲ませてあげても、彼女は一切感染しない。それは、彼女に対して神が一方的に授けた能力ではなくて、ある種の相互作用というか、彼女が宇宙の法則を巧みに利用していたんだと思います。マザーには、そうやって法則を上手に使うに足るたぐいまれな資質と才能が備わっていたのでしょうね。

白石:人間って、宇宙全体の法則を使ってごくごく私的に活動している生き物なんじゃないか、と最近よく考えるんです。今、遺伝子だけでは説明できない問題がいろいろと発生しているわけでしょう? だから、何らかの意思の集合体がある種のプログラムを組んで結晶化させて、「僕」や「出口さん」という物質的なものになっていると考えるのは決して荒唐無稽とはいえない。
そして、それは、いわゆる“神の意思”とどこまで関係があるかといえば、そこは「そんなには関係がない」のだろうと思います。神が知らないうちにそういうものをつくったか、神が知ってか知らずかつくったか、神が意図して自分とは関係なく勝手に動き回る存在をつくったか――。とにかく、特別な場合を除けば、神と人間に日常的なかかわりはあまりないんじゃないでしょうか。
出口:では、自分ではどうしようもない状況になったときに「神頼み」をしたりしますが、それも無効ということでしょうか?
白石:どうでしょう? 神が直接的に自分個人を救済してくれるとか、そういうことはなるだけ望まないほうがいいような気がしますね。自分を救済することができるのは、生まれる前の自分とか、生まれてからの自分とか、死んだ後の自分とか、とにかく「自分」だけです。要するに「救い」というのも個別化してしまえばある種のエゴでもあるわけです。
ただ、その「自分」が存在しているのは何らかの秩序立った法則にもとづいているわけですから、その法則に対して敬虔な気持ちをもち、何かとても困ったときに「その偉大な法則に素直に回帰する、復帰します」と念じるのは正しいと思います。それは「願い」というものではなく「祈り」と呼ばれるものですから、ある種の強力なパワーを秘めている。「祈り」はさきほどいった神と人間との双方向のエネルギー交換を可能にしてくれるのです。
なので、そのためにも内省的な自己をいつも保持しておくのは重要で、他人からいわれたことをそのまま鵜呑みにせず、自分で自分のことを見つめ、考え、「自分を新しくする」――ある種、自分を「デザイン」しながら生きることが人生においてはすごく大切なのだと思いますね。
ネコさえいれば結婚しなくてもよかった
出口:最新刊『君がいないと小説は書けない』(新潮社)では、白石さんと奥さまとの馴れ初めが描かれています。まさに運命のような出会いだと思いながら読み進めたのですが、当時は運命を感じていたのでしょうか?
白石:運命も何も、当時の僕はパニック障害を患っていて、ふとした瞬間に自殺してしまうんじゃないか、というような状態だったんですよ。だから、誰かに自分を監視してもらって、1分たりとも目を離さない状況を作り出す必要があったんです。
最初は友人の家に泊まっていたのですが、男同士だと同じベッドで寝ませんよね。だから、相手が寝ているあいだに、違う部屋で発作的に自殺してしまうかもしれない。そうなるともう、恋人をつくるしかありません。必死ですよ、自分がそんな状態にあったら。「速やかに監視役を確保するしかない」という気迫は彼女にも伝わったと思います。
出口:その人を好きという気持ちよりも、生命維持装置としての役割を求める気持ちが先行していたんですか……?
白石:いや、死にたくて仕方がない自分を止められるほどのエネルギーをもつ人を選んだわけだから、すごく偏った考え方でいうと「ものすごく好き」ですよね。それに、一緒に暮らし始めて、いざというときに助けてもらうと恩を感じるんです。そうすると責任を感じて、離れられなくなるんですよ。
ただ、最近は、自殺する可能性が高かったときにネコがいてくれたら、もしかしたら彼女がいなくても死なないですんだんじゃないのかな、と思うんですよね(笑)。いま、3匹のネコと一緒に暮らしていて思うのですが、動物って人間の代わりじゃなくて、それ以上の何かを提供してくれることもあるなと。ネコちゃんさえいれば、彼女と一緒にならなくてもよかったのかもしれません。
『君がいないと小説は書けない』を読めばわかるように、僕は全然おもしろい人生を送ってきていないんですよね。人と会わなくても、家から出なくてもストレスを感じないから、気をつけないと3カ月間、奥さん以外の誰とも会わないとかザラにある(笑)。僕ひとり、ずっとウィズコロナみたいな生活をしているんです。
ちなみに、『僕のなかの壊れていない部分』(光文社)の主人公・「僕」は、若いころの自分をそのまま書いているんです。あのころは、誰のことも好きになれなかったですから。
出口:えっ……。この作品を読んで、主人公に対して恐怖心を抱いてしまいました。
白石:そうでしょうね。それはいたってまともな反応だと思います(笑)。僕は、人間的な感情があんまりないんです。小説のなかでは親との複雑な関係性が影響して主人公があんな人になったわけですけど、僕にはそのような原因は何もなくて。人とかかわったりするのが得意ではなかったんですよ。というか、どちらかというと、みんな嫌いだった(笑)。
今も自分の核となる部分はあまり変わっていないですね。人とかかわらなくても平気だし、一生ウィズコロナ生活でも問題ない。人生、生まれてきて何がよかったって、ネコと出会ったことと甘いものが食べられることくらいですかね。
- 新刊情報
 『君がいないと小説は書けない』
『君がいないと小説は書けない』
勤めていた出版社の上司、同僚、小説家の父、担当編集者。これまで明かすことのなかった彼らとの日々を反芻すればするほど、私は自問する。私は、書くために彼らと過ごしていたのか。そして最愛の妻よ。とてつもなく圧倒的で、悲しいほど実感がない君のすべてを、私は引き受ける。神に魅入られた作家が辿り着いた究極の高み。 https://www.shinchosha.co.jp/book/305656/
この記事に協力してくれた人special thanks
-
白石一文
1958(昭和33)年福岡県生れ。早稲田大学政治経済学部卒業。文藝春秋勤務を経て、2000(平成12)年『一瞬の光』でデビュー。2009年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で山本周五郎賞を、翌2010年には『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞。ほかに『不自由な心』『僕のなかの壊れていない部分』『私という運命について』『火口のふたり』『神秘』『愛なんて嘘』『記憶の渚にて』『一億円のさようなら』『プラスチックの祈り』『君がいないと小説は書けない』など。 
まだデータがありません。