小説家・白石一文さん「たくさんのスイッチを1つずつ切るように生きていきたい」(中編)
直木賞作家が語る「自分をあたらしくする」ことと「死」の関係性

取材・文:出口夢々
写真:浅野 剛
前編で、「自分を新しくする」行為はいつでも、誰にでもできると語った、小説家・白石一文さん。自分を新しくした結果、それまで築いてきた地位や名声を失っても、それは破滅ではないし、そもそも「死」以外に破滅などない、といいます。
中編では、はたして死は本当に破滅なのか、絶対的現象である死とどのように向き合えばよいのかお聞きしました。
死を生のゴールと捉えて生きていく
白石:死ぬことによって肉体は滅びるわけですから、たしかに死ぬことは文字どおり「破滅」です。ですが、自分自身の終えんを考えることで、死を「目的化」するのは可能なのではないでしょうか?
出口:死を目的にして生きるのですか……?
白石:そう。「自分はどうやって死のうか」とか「どんなことを準備してから死のうか」と考えると、その行為そのものが死ぬことに対して積極的に働きかけるものになるわけですよね。そうやってポジティブな意味で「死を人生のゴール」と捉えられれば、死ぬことを自己の破滅だと思わなくなるんじゃないかな。
出口:「どうやって死のうか」という問題を考えるのは、自殺とか病気、もしくは自宅で死ぬか、施設や病院で死ぬのかといった「死に方」を考えるわけではないですよね?
白石:「死に方」ではなくて、「いかに死ぬか」ということですね。
僕は62歳なのですが、うちの父は72歳で死んでいますから、自分も父と同じ年齢で死ぬとすると残された時間はあと10年しかありません。そう思うと否応なしに「自分はどうやって死ぬのかな」と考えてしまうものなんですよ。でも、そのまま死という事象だけを捉えてしまうと恐怖心が生まれてしまう。そこで、死をゴールと捉えて、そこまでをどのように生きていこうか、考えることにしたんです。

出口:「どうやって死ぬか」を考えることが「どうやって生きるか」を考えることにつながる。
白石:そうです。そう考えてみると、死は突然襲ってくるものではなくて、生きた先にあるゴールとして捉えられるわけですよ。生と死が分断されているのではなく、地続きになっているイメージです。
では、どのようにゴール(=死)を迎えるのか――。親父が72歳で死んでいるわけだから、62歳の僕にとって「10年後に死ぬかもしれない」と仮定するのはかなりリアルなんです。だから、その10年間、自分がこの世で執着しているものを1つずつ手放していくことで、死ぬ準備ができるんだろうと思うんです。
いろんな欲があったわけですよ、僕だって(笑)。死んじゃうのにいつまでもギラギラさせていても仕方ないから、その欲を1個ずつ麻酔をかけるように眠らせていってあげないといけない……。最近そう考えるようになりました。
たとえば、宇宙船のコックピットをイメージしてみてください。コックピットのなかはスイッチだらけで、宇宙船の機能を停止させるためにはそのスイッチを1つずつ切っていきますよね。それを自分の人生に置き換えて、「どうやってこのスイッチを1個ずつ切っていこうかな」「どれを最初に切ろうかな」と考えてみる。そんなふうに、自分がやりたかったことを1つずつ始末をつけていって、10年経ったころには「最後の1つを押せば死ぬ」という状態になっている――。そんな生き方ができればいいなと思っています。
出口:始末をつけるというのは、欲望を叶えるということですか?
白石:いや、叶えなくていいんですよ。「やりきろう」と思っていたことを諦めるんです。
身体の機能って年齢を重ねるとともにだんだんと失われていきますよね。僕ってもう走れなくなっているんですよ。若い人たちを見ていてよく思うのは、彼らってやみくもに走っているんですよね。思い返してみたら、僕も彼女がタクシーに乗って帰るとき、よく追いかけて走っていたもの(笑)。
でも、これが今はできなくなっているわけです。若いころだったら信号が黄色だったら走って渡っていたけど、今だったら絶対に渡らないからね(笑)。そうやって身体は死に向かっていろんな機能をなくしていくわけです。
ですが、身体と違って心は自由にできているので、年齢を重ねるとともにひとりでに老いていってはくれないんですよ。だからスイッチを1つずつ切るようにして、心を衰えさせないといけない。そうすることで、だんだんと欲が薄くなっていって、欲が薄くなればなるほど死ぬことが怖くなくなる。「別に死んでもいいや」と思える境地に立てる。だから、何かを1つずつ心のなかで諦めていくっていうのは、とても楽しい作業なんです。
出口:楽しい……? 「諦める」という行為と「楽しい」という感情が結びつくイメージが湧かないです……。
白石:たとえば、ずーっと恋愛をしてきた人が「もう恋愛するのはやめよう」と思ったとしましょう。恋愛をしている状態というのは、欲望に首根っこを捕まれて、右往左往している感じですよね。欲望にドライブされている、といえるかもしれない。もちろんそれも楽しいんだけど、そういうジェットコースターから降りるという、別の楽しさがあるんですよね。
昔、文芸評論家の江藤淳さんに「白石くん、僕は性欲がなくなった。最高だ」といわれたことがあって。60歳とか70歳でも父親になれる人って、男からするとスーパーチャンピオンみたいな存在だけど、江藤さんは「まだ性欲に引きずられながら生きているなんて、かわいそうだな」というんです。そのとき僕は「はあ、そういう見方があるものか」と感心したんですよね。性欲を含め、いろんな欲望が薄くなっていくと、心が解放されて自由になるんです。
出口:たしかに、そうした欲望を抱かない境地というのは新鮮ですし、そういったものにとらわれない分、物事をよりフラットに考えられそうですね。
生まれることよりも死ぬほうがマシ
出口:死を目的化して、欲望を1つずつ眠らせていったら、死に対する恐怖は薄らいでいく――。まだ若いゆえか……私は死がとても怖いです。そんななかで、白石さんのその考え方は希望になります。
白石:出口さんはまだ若いんだから、おおいに死を怖がればいい(笑)。とはいえ、死ぬことって、生まれるより全然マシだと思うんですよね。というのも、人間っていうのは誕生時に「生まれる」っていう絶対的な現象を体験するわけですけど、それは自分がまったく関与していない現象なんです。
考えてみてください、僕たちは突然生まれているんですよ?(笑)
生まれた瞬間のことなんて忘れちゃうからいいんですけど、覚えていたら驚きですよね。だって突然目を開けたらわけのわからないところにいて、強い光を放つライトの下にはマスクをした助産師さんやお医者さん、看護師さんがいて。自分の姿を鏡で見たことがないから、そうした人たちはみんな怪物だとしか思えないですよね。そして挙句の果てには、身体を振り回されておぎゃあと泣かされてって、驚愕ですよ。ほんとうに怖かったと思います。しかも、こうした一連の流れは否応もなくやらされるので、「自分」というものはまったくどこにもないんですよね。

それに対して、死は、それを迎える直前までは自分の意思があります。「生まれる」のも絶対的現象でしたけど、「死ぬ」のも絶対的現象で、これには抗えません。ですが、よくわからず生まれてきたのに対して、自分で「死」というものを見据えて、それまでの過程も自分の意思のもと過ごせるわけですから、どのように死ぬのかをちゃんと選ぶのは当然だし、恵まれたことだと思いますよ。
人間って、とんでもなくひどい目にあってこの世界に入ってきて、ちょっとマシになって出ていくんですよ(笑)。
出口:この世界から出ていった先、つまり死後のことはどのように考えていらっしゃいますか?
白石さんの書かれた『私という運命について』(角川書店)では、主人公の旦那さんが亡くなったあと白馬に魂を移して、死後も自分の意識があることを奥さんに表明するシーンがあったり、『プラスチックの祈り』(朝日新聞出版)では、死者からの通達として電話が鳴るシーンを描かれていますよね。
白石:根拠を論理的に説明することはできないのですが、「死後の世界があるかないか」と訊かれたら、私は「ある」というと思います。
- 新刊情報
 『君がいないと小説は書けない』
『君がいないと小説は書けない』
勤めていた出版社の上司、同僚、小説家の父、担当編集者。これまで明かすことのなかった彼らとの日々を反芻すればするほど、私は自問する。私は、書くために彼らと過ごしていたのか。そして最愛の妻よ。とてつもなく圧倒的で、悲しいほど実感がない君のすべてを、私は引き受ける。神に魅入られた作家が辿り着いた究極の高み。 https://www.shinchosha.co.jp/book/305656/
この記事に協力してくれた人special thanks
-
白石一文
1958(昭和33)年福岡県生れ。早稲田大学政治経済学部卒業。文藝春秋勤務を経て、2000(平成12)年『一瞬の光』でデビュー。2009年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で山本周五郎賞を、翌2010年には『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞。ほかに『不自由な心』『僕のなかの壊れていない部分』『私という運命について』『火口のふたり』『神秘』『愛なんて嘘』『記憶の渚にて』『一億円のさようなら』『プラスチックの祈り』『君がいないと小説は書けない』など。 
まだデータがありません。


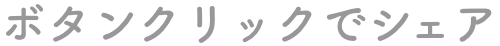
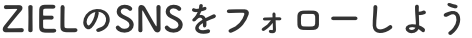













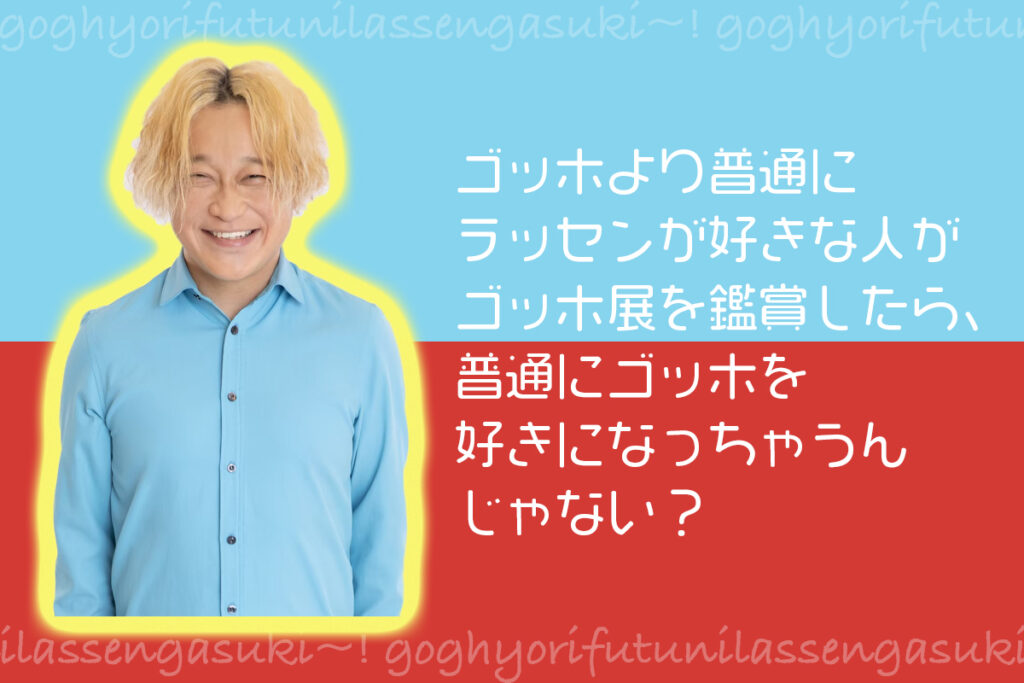





[…] 中編へ続く […]
[…] 中編で、死を「目的化」し、人生のゴールとして死を設定すれば、将来絶対に訪れる死への恐怖心を薄くできるのではないかと語った小説家・白石一文さん。後編では、私たちは死んだ […]