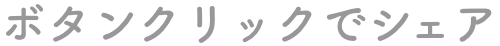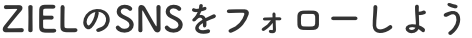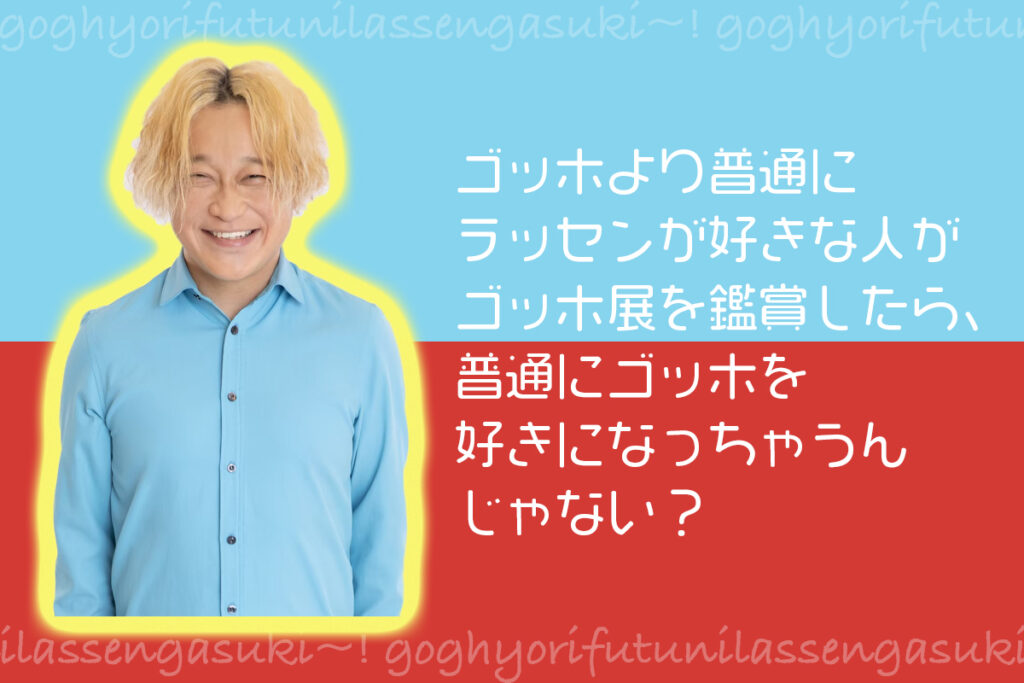モーパッサン『女の一生』から学ぶ女性の生き方
ジャンヌに秘められた「運命を受け入れる力」
――現実に不満を抱えるあなたへ

取材・文:出口夢々
古典文学作品から生きる知恵や教訓を学ぶ連載企画、「文学から学ぶ、女の一生」が始まりました! 編集部が選んだ作品を研究している方にインタビューを行い、その作品の読み方や読みどころを教えてもらいます。
記念すべき第1回目は、連載タイトルにもなっているモーパッサンの『女の一生』を読んでいきます。モーパッサンは19世紀フランスで活躍した小説家。皮肉的な表現と自然描写が得意だったと言われている作家です。そんなモーパッサンがはじめて書いた長編小説『女の一生』について、19世紀フランス文学を研究している慶應義塾大学文学部教授の小倉孝誠先生にお話を伺いました。

男性の所有物だった19世紀の女性
私にとって『女の一生』とは、19世紀前半のフランスを生きた1人の女性の物語であると同時に、当時のフランス社会のあり方も照らし出してくれる作品です。
この物語は、主人公のジャンヌが修道院を出て、家族とともにフランス北西部・ノルマンディー地方の土地、レ・プープルへ向かう場面から始まります。修道院と聞くと、修道女になるために入る場所かと思うかもしれませんが、当時のフランスではお金持ちの子どもが読み書きを習うために幼少期を過ごした場所でした。男爵家の一人娘として生まれ、何不自由なく育ったジャンヌ。レ・プープルのお屋敷では、夢想しながら幸福な生活を送っています。そして、そこで出会った子爵・ジュリアンと結婚しましたが、幸せな結婚も束の間。夫は浮気をし、息子は放蕩を極め、ジャンヌは過酷な人生を歩まざるを得なくなりました。
あらすじだけ読むと、ジャンヌの人生はあまりにも不幸だと思う方もいるかもしれません。ですが、これは当時のフランスに暮らす貴族女性には、よくある人生。モーパッサンが、フィクションとして不幸な女性の人生を描いたのではないのです。
この作品が発表された1883年のフランスは、「リアリズム」や「自然主義」と呼ばれる文学の時代にありました。人間や社会、時代、家族——そうした「現実」を理想化せずに、否定的な部分や悲観的な部分も含めて、ありのままに語ることを目指した文学の流れのなかにあったのです。
そして、当時のフランスでは、女性はまだまだ弱い立場にありました。ジャンヌとジュリアンが初夜を迎える日に、男爵がジャンヌに対し「お前は全部夫に属しているものなのだよ」と語りかけますが、これは身体的な話に限ったことではないのです。
当時は上流階級になればなるほど男の世界。女性は男性の所有物として存在していました。ジャンヌも、幼少期から少女期までは父親である男爵の言うことが絶対という世界で生きていましたし、結婚してからは夫のジュリアンがジャンヌの財産を管理し、使いましたよね。そして、男の子の子どもが生まれたらその子がいずれは家長となり、家を切り盛りしていく。女性は、子どものうちは父親に従い、結婚したら夫に従い、老いれば息子に従う——。そのような社会的風習が根強く残っていたのです。
「夫がどうしようもない人なら、さっさと離婚してしまえばいいのに」と思う方もいるかもしれませんが、当時のフランスは離婚ができない時代でした。1816年から1884年は法律で離婚が認められていなかったのです。ですので、一度結婚してしまったジャンヌには、夫の浮気を見て見ぬふりをしながら生きるという選択しか残されていなかったのでした。
社会的背景の違いに目を向けて読む
このように、ジャンヌの人生だけでなく、物語が展開されている時代の社会的背景や描写に目を向けると、文学の楽しみ方はグッと広がります。
この物語のなかで、とりわけ私の印象に残っているのは、フルヴィル伯爵が羊飼い用の移動小屋を谷底へ落としてしまうシーンです。この移動小屋のなかで、浮気関係にあったジュリアンとフルヴィル伯爵夫人が逢瀬をしていたのですが、この2人をなかに閉じ込めたまま伯爵は小屋を谷底へ落としてしまうわけですよね。その後、顔がぐしゃぐしゃになった2人が見つかり、死亡が確認されますが、伯爵が逮捕されたりまわりの人に疑いの目を向けられるような描写はありません。それは、当時のフランスにおいて、夫は自分の妻が不貞を犯している場面を見てしまったら、制裁を加えても罰を受けなかったからです。
もちろん、不貞を働らくことはよいことではないのですが、同じように不貞を働いても、男性と女性では法律上の扱いが異なりました。たとえば、夫が妻の浮気現場を捕らえてしまったら、妻をどうしようが自由。極端な話ですが、殺してしまっても罪には問われませんでした。一方、妻が夫の不貞を現行犯で捕らえて、夫を殺してしまったら罪に問われます。
このように、当時のフランスでは同じ罪を犯したとしても、男女で法律上の制裁が異なりました。だから、フルヴィル伯爵が自分の妻とジュリアンを殺してしまったときに、仮に周囲の人が犯人は伯爵だと気づいていたとしても知らないふりをして過ごす。それが当時の社会だったのです。

また、多くの人が疑問を持つであろうと思うのは、ジャンヌとロザリの関係性です。ロザリはジャンヌの乳姉妹で召使い。そんなロザリが、ジュリアンと浮気をし、子どもを身ごもってしまったので屋敷を離れることになります。ですが、物語の最後、両親も夫も息子も失ったジャンヌのもとにロザリが戻ってきますよね。そして、ジャンヌはそれを喜ぶ。
この場面を読んで、「夫の浮気相手の再訪を喜ぶなんて、どのような人間関係なのだろう」と思う人もいるかもしれません。ですが、きっと、ジャンヌにとっては、ジュリアンがロザリと関係を持ったことよりも、フルヴィル伯爵夫人と関係を持っていたことのほうが嫉妬の種だったと考えられます。
というのも、ロザリはジャンヌの召使いですから、ジャンヌとはまったく階級が異なる存在です。当時は階級社会でしたから、「階級が違うと人間性が違う」という認識が人々のあいだに強くありました。そして、階級が異なると、嫉妬やライバル心のあり方が変化するのです。人間には、自分と似たようなものに対して、あるいは自分と似たような環境や集団に対しては妬みを感じやすい特性があります。ただし、まったく別の世界になってしまうと、そのような感情が生まれづらいのです。
ですので、近所に住んでいる同じ階級のフルヴィル伯爵夫人とジュリアンが関係を持っていたことのほうがジャンヌの悩みの種であったと思いますし、ロザリと関係を持ったこと以上にショックだったと思います。夫が自分と同じ階級の人と関係を持ってしまうことの許し難さがあったのではないでしょうか。
また、ジャンヌはいわば世間知らずのお嬢さま。家族がみんないなくなってどうすればよいかわからなかったときに現れたロザリは、救世主のように見えたかもしません。ロザリは庶民の知恵を持っていましたから、何もわからないジャンヌにとってその存在は大きかったのでしょう。
ジャンヌに秘められた「受容する力」
ジャンヌの姿を見ていると、どうしても歯痒い気持ちになったり「なんて主体性に欠けた女性なんだ」と思う人もいるでしょう。ですが、ジャンヌの姿からは「人生を受け入れることの重要性」や「人生を受け入れる者に迫る覚悟」なども読み取れます。物語の最後の「なんのはや、世の中というものは、そんなに人の思うほど善くもなし悪くもなしですわい」というロザリのセリフに賛成する人が多いとは思いませんが、残念ながら、人生は自分個人の力ですべてを変えられるわけではありません。ですので、過酷な人生を受け入れながら生きていくジャンヌから「運命を受け入れる力」を学べるのではないでしょうか。
古典的な文学というのは、何かに悩んでいるときや、何か困難な状況にあるときにいろいろなことを考えさせてくれます。『女の一生』は安直な慰めにはならないかもしれませんが、人生を長い目で捉えたときに自分で自分の問題を解決していく際の心構えのようなものを教えてくれる作品です。
また、現在、新型コロナウイルスの流行で世の中が大変な状況にありますが、そんなときでも、人生に絶望しないことの重要さも教えてくれる作品でもありますね。たしかに、ジャンヌのように絶望にかられることもある。ですが、人生、常にうまくいくことばかりではないですから、ジャンヌのように挫折や失敗、躓きを受け入れ、生きていくことも必要なのかもしれません。
『女の一生』が教えてくれる、女性の生き方
・19世紀のフランス人女性は男性の所有物だった
・自分自身で自分の問題を解決する主体性の有無が人生の明暗を分ける
・挫折や失敗、躓きを受け入れ、生きていくこともときには大切
この場面が好き!
ジャンヌが修道院を出て、レ・プープルのお屋敷に到着した日の様子として描かれている植物や海、森などの描写は本当に美しいので、とりわけ好きな場面です。
ノルマンディー地方出身のモーパッサンは、海や森や植物など、さまざまな自然に囲まれて育ってきました。ですので、その経験が生かされた描写が物語内にふんだんに出てきますよね。ジャンヌとジュリアンが新婚旅行として訪れたコルシカ島の場面もとても美しい自然描写がなされています。
また、この小説が書かれた1880年代は、印象派の画家であるモネやルノワールなどがノルマンディー地方を訪れ、その風景を描いていた時代です。光が戯れる様子や海の輝き、森や樹木の描写——。そうした印象派の絵画の特徴と、モーパッサンの自然描写に共通点を見出しながら読んでもおもしろいでしょう。クロード・モネ ≪サン・タドレス:浜辺のテラス≫
モネがノルマンディー地方のル・アーブルで描いた作品
『女の一生』を読んだら、ぜひ感想をコメント欄で教えてください!
この記事に協力してくれた人special thanks
-
小倉孝誠
慶應義塾大学文学部教授。1956年生まれ、青森県出身。1988年、東京大学文学部助手。1989年、東京都立大学人文学部助教授。2003年、慶應義塾大学文学部教授、現在に至る。2011年日本翻訳出版文化賞、2018年福澤賞。専攻はフランスの文学と文化史。主な著書に『愛の情景』(中央公論新社、2011年)、『革命と反動の図像学』(白水社、2014年)、『写真家ナダール』(中央公論新社、2016年)、『ゾラと近代フランス』(白水社、2017年)、『逸脱の文化史』(慶應義塾大学出版会、2019年)など。 
まだデータがありません。